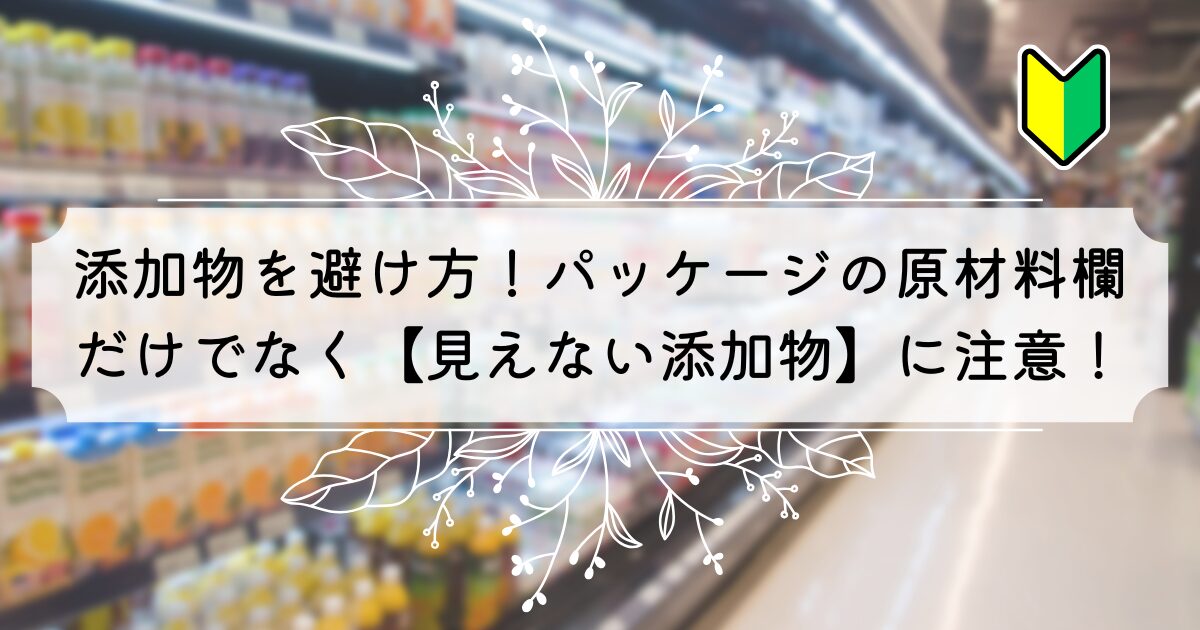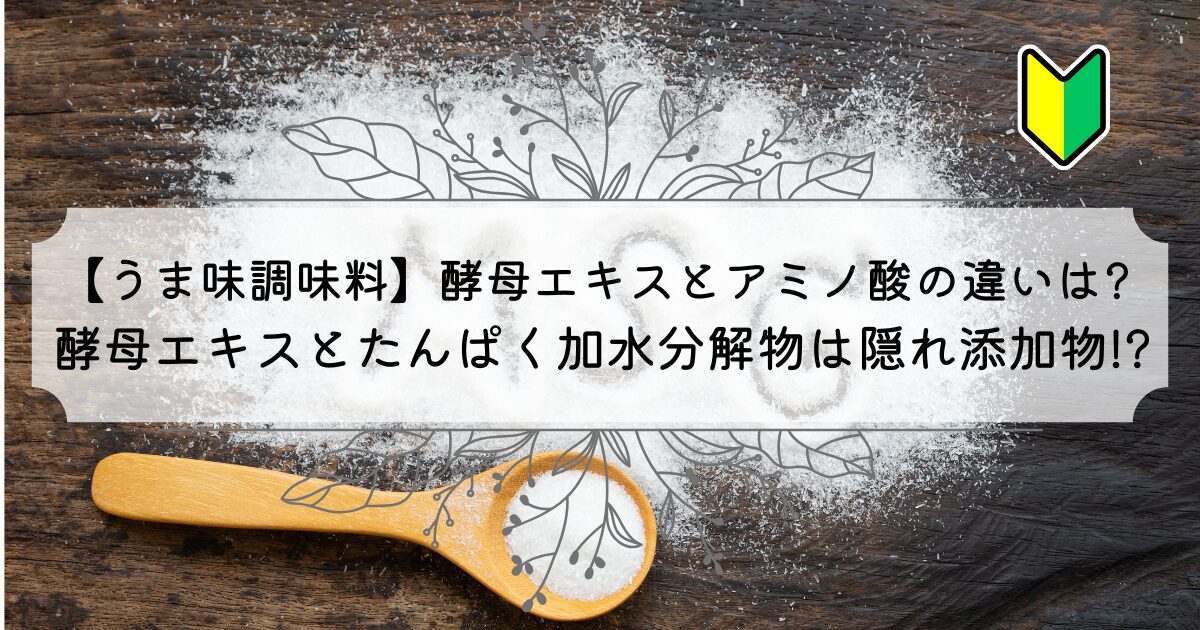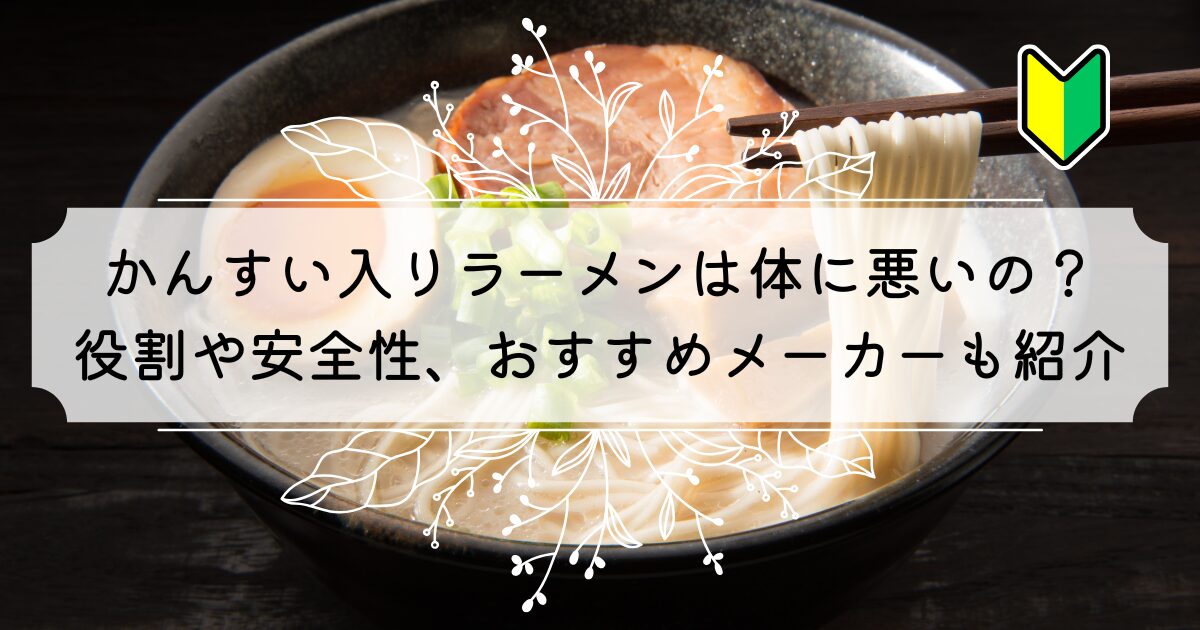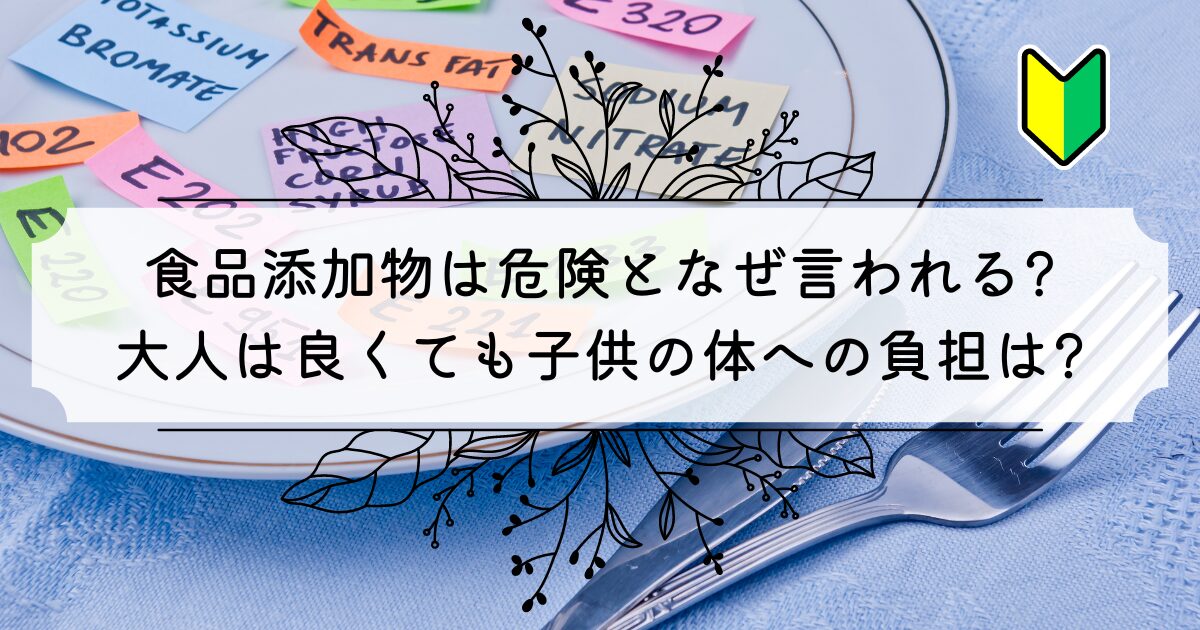ポストハーベストとは?身近な小麦粉など残留が心配な食品と対策
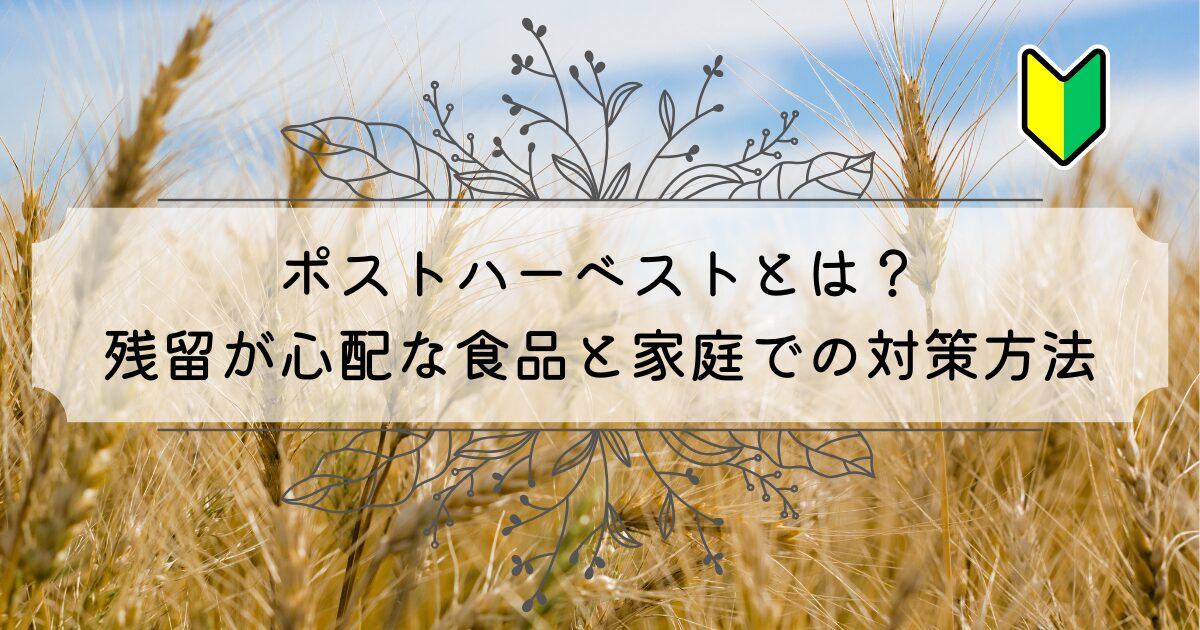

よく出てくるけど、ポストハーベストってなに?
外国産の『収穫後の作物』は、遠い日本にくる前にカビや害虫や腐敗を防ぐため、作物自体に農薬が散布されます。
そしてこのポストハーベスト農薬は、残念なことに栽培中に使われる農薬よりも残留の可能性が高いのです。
お米が高くなり、麺やパンなど小麦粉製品を食べる機会が増えた家庭も多いのではないでしょうか。
なかでも国内消費量の9割が外国産の小麦粉には注意が必要です。
子どもが小さいうちは、親が与える食品が子どもの体を作ります。
ポストハーベストも、気をつけてあげたい食品選びのポイントのひとつです。
小麦粉をはじめ、輸入の食品が高騰している今こそ、国産の食品を応援するべきなのです!
農薬の残留の可能性が高い輸入食品と、その対策をご紹介します。
ポストハーベストとは?

収穫(ハーベスト)された後(ポスト)の果物や穀物や野菜に直接まかれる農薬のことを指します。
日本へ輸出するためには、長い長い渡航期間がかかります。
その間、害虫による被害やカビなどによって、商品として売り出せない状態にならないようポストハーベスト農薬をほどこすのです。

もちろん消費者をカビ毒から守るためでもありますが、利益のための方が大きいかな…
ポストハーベストの種類
ざっくりですが、こんな作用のあるポストハーベストがあります。
- 作物の成長を止めるもの
- カビ防止・防腐のための殺菌剤
冷蔵庫の中で長ネギも伸びるし、ジャガイモも芽が生えてしまいますよね。
野菜も植物なので、収穫後も生きようとしています。
成長してしまえば、当然味も落ちるし見た目も悪いし売り物にならないのです。
殺菌剤は防腐剤・防カビ剤として、こんなものがあります
- イマザリル(IMZ)
- チアベンダゾール(TBZ)
- オルトフェルフェノール(OPP)

あー!オレンジとかによく書いてあるよね!

具体的にどんな作物(食品)に使われているか次でチェックしましょう
ポストハーベスト残留の可能性が高い食品

ポストハーベスト農薬は、知らないだけでたいていの輸入作物に使われています。
その中で、残留の可能性が高い食品にはこんなものがあります。
(農薬が自然にもしくは加工によって消えきらず、残ってしまうことを残留といいます。)
- 小麦・米
- とうもろこし・ジャガイモ・かぼちゃ
- 大豆・ナッツ
- オレンジ(柑橘類)・バナナ・サクランボ
輸入時に使われているポストハーベストは、なんと添加物扱い。
そのため、加工されずバラ売りされるフルーツなどには添加物として表示されていることがあります。
『小麦を製粉する』『大豆を豆腐にする』『ナッツの殻をむいて炒る』
ひとたび加工されてしまえば、もう原材料の一部となってしまう。
防腐剤防カビ剤などのポストハーベストは表示する義務はなくなってしまいます。

だからオレンジ以外の印象がないのか…
- その他にも、こんな理由で使われる!
-
レタス・ブロッコリー・アスパラなどの
『普通に冷蔵庫に入れていても日もちが悪い野菜』や、
逆に『冷蔵して保管すると低音障害をおこす暖かい地域の作物』にも。
冷凍の野菜・フルーツなら大丈夫か?と思いきや、貯蔵の時点でもうポストハーベスト農薬がかけられていることも多い。
小麦粉にはプレハーベストも使われているかも
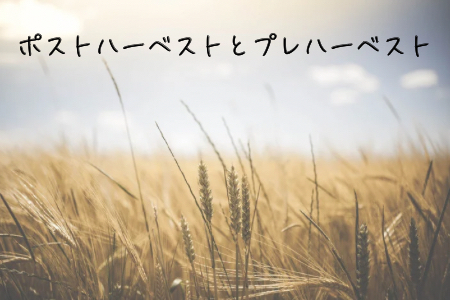
残留の心配がある小麦ですが、なんと国内消費量の約9割が外国産です。
お菓子、麺、菓子パン…ほぼ外国産小麦の小麦粉で作られていると思ってよいでしょう…。
なぜ特別に外国産小麦粉を危険視しているかというと、
ポスト(収穫後)に加えて、プレ(収穫前)にもかける農薬もあるんです!
これは慣行栽培の農薬とも意味合いが違い、収穫したい時期の調整のために使っています。
- 収穫時期を調整したいってどんな状況?
-
例えば『大雨が降る・台風(ハリケーン)の予報がある』→『小麦が水分を含んでしまう・商品にならない可能性がある』→『収穫時期が遅れる・早く刈り取りたい』
というように、根がついた状態の小麦の乾燥を早め、枯らすのです。
プレハーベストは主に除草剤のことですね。

これまた残留量は『人の健康に悪影響とはいえないほど微量』だから大丈夫だそうですが…

それにしてもできることなら『残留はない』に、こしたことはないね…
幸いにも、現在の日本の小麦栽培ではプレハーベストの使用は認められていません。
私も家庭で使う小麦粉は特別な理由がない限り国産を選んでいます。
ポストハーベストの問題点


添加物同様、厚生労働省は健康に悪影響がないとされる『ADI値』を設定はしています。が…
そう。たしかに、気にし過ぎはよくないです。具合悪くなっちゃいます。笑
でも、ADI値は設定していても保証はしてませんし、やっぱりポストハーベストについては知っておいたほうが良いと思うんです!
ポストハーベストの問題点は身体への影響の他にも色々あるんですが、知っておいてほしいことが大きく3つあります
病気やアレルギーの原因となりうる
発がん性が疑われていたり、現地(外国の生産地)では奇形児が生まれる原因となったとも言われています。
畑で使われる濃度の100〜数百倍で使われている
慣行栽培(農薬を使う栽培)でも、農薬の残留はもちろんあり得るのですが、多少の農薬なら日光や土の微生物の力で分解されていきます。
ですが刈り取った後に振りかけられてしまえば、なかなかそれは難しくなります。
簡単には洗い落としきれない
買った輸入の食材が心配であれば、色々洗浄方法はありますが…
- 熱湯にくぐらせたり
- 塩もみして洗ったり
- 野菜・果物用洗剤を使って洗ったり など
ですが実際はなかなか落ちきらないようです。
野菜・果物用洗剤には、石鹸系の食器用洗剤と兼用のものや、貝カルシウムを溶かして漬け込むタイプなどがあります。

おぉ…泡つけて洗うのは、なんか勇気いるね…

洗ったら洗ったで目に見える農薬に後悔しそうで、実は私もやったことがありません。笑
ポストハーベストの家庭での対策3つ

手軽にできるポストハーベスト対策を3つお伝えします。
対策というよりも、これは食材選びの日常習慣にしてほしいです!
国産・旬のものを食べよう
幸いにも日本国内でのポストハーベストの使用は認められていません。
国産のもの、できるだけ、地元の物を買って、食べて応援しましょう。
『地産地消』という言葉は、学校の社会科で習いましたよね。
それがポストハーベスト対策になるし、農家さんへの応援にもなるし、日本の自給率を上げる一歩になります。

輸入品が高くなりつつある今がチャンス。そんなに値段が変わらない程度なら、国産を選んで!
また、旬のものは栄養価も高く、安く手に入りやすい時期でもあります!
輸入のおかげで年中買うことができるのはありがたいこと。それは間違いないですよね!
ですが、その時期にしかとれない野菜や果物で四季を感じることは、『食育』としても良いのではないでしょうか。
たとえば外国産が主なキウイフルーツも、2月ごろから国産が出回ります。

私も冬は無理にメキシコ産のアスパラガスを買って食べません
「有機野菜、化学農薬・肥料不使用野菜は、化学農薬・肥料の力によって無理に成長させられていないので日もちが良い」
なんてよく言われています。(実際すべてがそうとは限りません)
こちらをご覧ください

ズボラな私に(ラップもせず)冷蔵庫で忘れ去られていた、農薬不使用栽培の国産レモンが最近見つかったのですが、購入から48日経過してもこの状態でした。
健康的に育ったレモンには、防腐剤…いらないですね 笑
原産地表示・パッケージをしっかりと見る

食品選びの基本ですが、パッケージは裏もしっかりと見ましょう!
スーパーのプライスカードには原産地やポストハーベストの情報も書いてありますよ。
できるだけ、どこのだれが作ったものかをしっかりと明示されているお店で買い物するようにしましょう。
よ〜く品物を見ていると、売れ筋ばかりを置いているスーパーと、地元のものを積極的に取り入れているスーパーがありますよ。
また、外国産でも有機・オーガニックの認証を受けた食品は、ポストハーベストの心配はありません。

ナッツやバナナなど国産を見つけるのが難しい食品は、有機を選ぶと良いね!
食材の皮を厚めにむく
外国産の果物を買ったりもらった場合は、皮を厚めにむいて食べましょう。
特に外国産の柑橘類は注意が必要です。皮を器にしたり、紅茶に輪切りレモンを入れるのはおすすめしません。
ジャムやクッキー作りなどに皮ごと使用したいときは、有機認証のものか国産の柑橘類を選んでください。
野菜・果物用の専用洗剤について
さきほどポストハーベスト農薬は「落としきれない」とはご紹介しました。
ですが、野菜・果物専用洗剤で洗うことで『ポストハーベスト農薬』や『栽培時の残留農薬』は少し落とすことはできます。
洗うことで気持ちは楽になるかもしれませんが、批判覚悟で言います…

そこまでやるなら、有機の野菜・果物以外は買うな!
農薬が心配で全野菜を「洗剤で洗わなきゃ!」ってやってたら、ノイローゼになっちゃいますよ。
切って水にさらしたり茹でたりすることで、栽培時の農薬はある程度なら落ちるようです。
特に果物は完全農薬なしでの栽培が特に難しいです。収穫までの農薬をまく回数が半分でも拍手って感じ。

そうだね。気にはなっちゃうかもしれないけど、おいしくいただけることに感謝の気持を忘れないでいきましょ〜
まとめ

ポストハーベストとは、収穫された後の果物や穀物や野菜に、直接まかれる農薬のこと
- 病気やアレルギーの原因になりうること
- 畑での栽培に使う濃度の100〜数百倍で使われること
- 洗っても簡単には落としきれないこと
- 地産地消を意識し、国産の食材を選んで買う(できれば旬のもの)
- 原産地表示やパッケージ裏をしっかりチェックする
- 果物や野菜は皮を厚めにむいて食べる
- 有機認証を受けた食材は、ポストハーベスト農薬の心配はない
輸入のおかげで、一年中食べたい野菜や果物を手に入れることができる豊かな時代となりました。
そのありがたさを感じるとともに、やはり『便利』には代償がつきものなのだなとも思ってしまいますね。
食育の一環として、ぜひお子さんと『旬の食材』を調べたり、『地産地消』を親がしている姿をみせていくことが大事なのではないでしょうか。